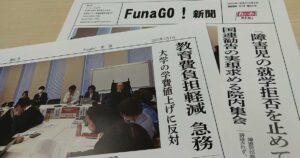2025年2月21日 障害児を普通学校へ・全国連絡会主催の「国連2022年総括所見(勧告)の実現を求める院内集会」に参加
2月21日、障害児を普通学校へ・全国連絡会主催の「国連2022年総括所見(勧告)の実現を求める院内集会」に参加しました。障害があってもなくても地域の学校で共に学び、育つことを目指して活動してきた障害当事者、親、教職員、これから就学を迎える親子、市民などが会場があふれるほど集まりました。舩後議員にとっては議員就任以来一貫して取り組んできた課題で、集会参加を通じて改めて、インクルーシブな社会実現への思いを強めました。
国連・障害者権利委員会の勧告では、現状の「分離教育」をやめ、インクルーシブ教育への転換を求めていますが、政府は「特別支援教育を直ちにやめるつもりはない」「多様な学びの場を整備していくと」して受け入れておらず、今も普通学級の就学を拒否される事例が後をたちません。こうした現状を踏まえ、国連からの勧告を実現するよう政府に働きかけることを目指して開催されました。
れいわ新選組からは舩後議員だけでなく、木村英子議員も出席。また、天畠大輔議員、大石あきこ議員の秘書さんも参加されました。
舩後議員はあいさつで、総括所見を起草した国別報告者のヨナス・ラスカス氏の「障害の有無で分離した特別支援教育は、インクルーシブな社会で暮らしていく道のりを否定し、将来、施設で暮らすことにつながる。インクルーシブ教育なくして、障害のある人の自立生活はあり得ない」のことばを紹介し、「インクルーシブな社会を創る土台は、小さい時から共に学び・育つことであることは、今や国際社会の共通認識だ」と訴えました。
「国連2022年総括所見の実現を求める院内集会」にお集まりの皆様こんにちは。れいわ新選組、参議院議員の舩後靖彦でございます。
2022年の夏、私も障害児を普通学校へ・全国連絡会さん他、百名を超える市民団体の皆さんとともに、国連・障害者権利委員会の対日審査の傍聴のために、ジュネーブに行ってまいりました。今日ご参加いただいている皆様の中にも、ジュネーブでお会いした方がいらして、あの時の熱気と興奮を思い出しました。
市民団体からのパラレルレポートやジュネーブ現地でのロビーングのおかげで、総括所見においては65項目の詳細な懸念と的確な勧告が出されました。総括所見は日本の障害者の人権状況を浮き彫りにしたものであり、特に、フォローアップで緊急措置を必要とされたのが、19条「自立生活と地域社会へのインクルージョン」と24条「教育」です。
このことについて、日本政府への総括所見を起草する報告者の一人、ヨナス・ラスカス委員は来日講演の中で、「障害の有無で分離した特別支援教育は、インクルーシブな社会で暮らしていく道のりを否定し、将来、施設で暮らすことにつながる。インクルーシブ教育なくして、障害のある人の自立生活はあり得ない」とはっきりとおっしゃいました。
障害者権利委員会が求める誰も排除しない、全ての人が地域社会で自由と尊厳をもって自律的に暮らせるインクルーシブな社会。施設入所や長期にわたる精神科病院への入院を必要としない社会を創る土台は、小さい時から共に学び・育つことであることは、今や国際社会の共通認識となっています。このことは皆様が取り組んできたことの基礎であり、私も議員活動の基本として確信しております。
しかしながら、文科省はこの勧告について「現時点において、特別支援教育を中止することは考えていない」。「障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に過ごす条件整備と、教育的ニーズに応じた多様な学びの場の整備を両輪として取り組んでいく」と、相変わらず多様な場に分ける特別支援教育にし、インクルーシブ教育への転換を無視し続けています。
私は、参議院議員になってから5年半、文教科学委員会や各地での集会を通じて、①障害のある子の普通学級就学を拒否できない就学先決定のしくみの整備、②共に学ぶための環境整備と必要な合理的配慮と個別支援の保障、③高校の定員内不合格をなくす、④インクルーシブ教育システムからインクルーシブ教育への制度転換、に取り組んできました。
粘り強く委員会質問を重ね、環境整備と合理的配慮、高校の定員内不合格問題に関しては、文科省も対応の変化があり少し進んだ感はありました。しかし、就学先決定に関しては1ミリも動いていません。
日本政府は次回、2028年2月20日までに政府報告の提出を求められています。それまでにどれだけ障害関係法制の見直し、障害者の権利の推進に役立てていけるか、立法府の役割は非常に大きいと認識しています。
まずは希望する子の普通学級入学を拒否できない仕組み、法制度整備に向けて、皆様の体験やお知恵をお寄せいただき、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
また、議員就任からの5年間での取り組みを紹介し「合理的配慮の提供、高校の定員内不合格問題に関しては、文科省も対応の変化があり少し進んだが、就学先決定に関しては1ミリも動いていない」と悔しさをにじました。そのうえで「まずは希望する子の普通学級入学を拒否できない仕組み、法制度整備に向けて、皆様の体験やお知恵をお寄せいただき、引き続き取り組みたい」と強調しました。
集会では、インクルーシブ教育に詳しい東京大学の小国喜弘さんと東洋大学の一木玲子さんや、DPI日本会議の尾上浩二副議長、実際に普通学級で学んだ大阪・豊中の上田哲郎さん、教員で「どの子もともに普通学級へ!ともに歩む会(帯広)」の吉田淳一さん、元教員で「知的障害者を普通高校へ北河内連絡会」の松森俊尚さんからそれぞれのお立場からの提言をいただき、その後会場からの意見・質問がたくさん寄せられました。
集会の最後には、障害児の就学・転入希望の拒否をしないことや、高校の定員内不合格をなくすことなど、5項目を文科省と政府に要請するアピール文を採択し終了しました。
舩後議員は集会に参加し、参加者の熱気と声を国会・文部科学省に届け、共に取り組んでいくことを誓いました。